
企業に欠かせないロゴデザインのプロセス
会社のロゴ、変える?変えない?
突然ですが、ご自身の会社のロゴを気に入っていますか?
名刺や封筒、看板、ウェブサイトなど、様々な場所で使われている自社のロゴ。
気に入っている人もいれば、なんとなく「カッコ悪い」「地味かも」「会社に合っていない」など、漠然とした不満を感じている人もいるかもしれません。
スタイルメントでは、企業やサービスのロゴをデザインさせていただくことも多く、今のロゴを作り直すのか、あるいは使い続けるのか、そこからご相談いただく場合もあります。
ロゴは単なる飾りや記号ではなく、企業のアイデンティティを形づくる重要なビジュアルの一部であり、まさに「企業の顔」であり「事業の視覚化」だと言えます。
近年、多くの企業がロゴのデザインを刷新していますが、その背景としてブランドの刷新、時代の変化への適応、デジタルデバイスへの対応、グローバル展開、そして企業の成長や事業の多角化など、さまざまな戦略的な理由があります。
ロゴのデザインを変えることは、単に見た目が変わるだけではなく、企業のあり方やこの先の未来を大きく左右する決断であり、ブランドの再認識または再構築という大きな枠組みの中で検討されるべきものです。
さらに新しいロゴは、顧客に対して競合との差別化を図るだけでなく、社員の意思統一や意識改革にもつながるものです。
今回は、企業の担当者の皆さんに、スタイルメントがロゴ制作に携わる中で大切にしていることやその制作プロセス、ロゴをデザインするうえで知っておいてほしいことをお伝えしたいと思います。
ロゴを新しくするうえで考慮すべき3つの視点
ロゴを刷新するには、まず現状どのような課題があるのかを把握することが重要です。もちろんロゴの前に企業のCI(コーポレートアイデンティティ)の見直し、商品やサービスなどのブランド分析やペルソナ設定も欠かせませんが、ここではロゴのデザイン自体に焦点を当ててお話していきたいと思います。視点としては「構成要素」「機能性」「感情面」の3つが挙げられます。以下、それぞれの視点から検証項目を整理します。これらの観点は新しくデザインしたロゴを評価する際にも有効となってきます。
1.構成要素
ロゴを構成する各要素を見直すことで、ブランドの在り方やメッセージをより的確に伝えることができます。
ネーミング
社名や表記が適切かを検討します。現在の社名が本当に相応しいかを見直すきっかけになる場合もあります。社名を変更しない場合でも、ロゴにおける表記を再検討する必要があります。正式な会社名とロゴの表記は必ずしも一致する必要はないのです。
例:「トラベラー株式会社」を「トラベラー」や「Traveler」と表記変更するケース。
シンボルマーク
ブランドイメージを象徴する重要なビジュアル要素です。最近はシンボルマークを持たない文字だけのロゴも多くなってきていますが、必要かどうかも含めて検討する必要があります。
例:黒猫(ヤマト運輸)、3つの菱形(三菱グループ)、カラフルなG(Google)、食べかけのリンゴ(Apple)など。
見ただけでブランドを瞬時に想起できることが重要です。
モチーフ
主にシンボルマークに関わることで、デザインするうえで何がモチーフとなっているかを定義します。
例えば地道な努力が得意な企業なら亀やミツバチをモチーフにデザインしたり、逆にフットワークの軽さや対応力ならウサギや犬が良いかもしれません。または食べ物や自然といった物質、愛や強さといった価値観や理念、それらを造形として的確に表現できているか見直します。
タイプフェイス
使用書体が企業のイメージやシンボルマークと合っているか。
例えば力強い社風に繊細な明朝体は違和感があるなど、好き嫌いではなく客観的な検証が必要です。
色
いわゆるコーポレートカラーと言われるもので、ロゴマークとセットで用いることで企業のイメージを強く印象づけます。あえて色を決めない場合もあります。
例:コカ・コーラ(赤色)、ローソン(青色)、ヤマト運輸(黄色と黒)。
タグライン
ロゴに添えられる短いフレーズのことで、企業やブランドの 特徴・理念・強みを端的に表すキャッチコピー です。必ずしも必要ではありませんが、特に強く訴えかけたいメッセージがあればタグラインとしてロゴとセットで用いる場合もあります。
例:味の素「あしたのもと」、マクドナルド「i’m lovin’ it」、ニトリ「お、ねだん以上」。
2.機能性
ロゴはさまざまな人の目に触れ、あらゆる環境で使用されるため、実用面での高い適応力が求められます。
汎用性
モノクロや反転使用、英語表記、背景色の違い、時には劣悪な環境など、あらゆる形態と場面で違和感なく展開できるか検証します。
視認性
遠近や縮小拡大でも判別できるか、文字が読みやすいか、周囲に埋もれないかを確認します。
普遍性
流行に左右されず、長期に渡って使えるか。国や文化を越えて同じメッセージを伝えられることが重要です。また、ターゲットの年齢層を限定しない場合はあらゆる年代に受け入れられる柔軟性も必要です。
シンプルさ
複雑すぎると覚えられないし、単純すぎると平凡になります。そのバランスが取れていることが重要です。
競合との対比
他のロゴと似ていないか広範囲にわたってリサーチを行う必要があります。特に競合他社との類似性には注意します。
オリジナリティ
そもそもロゴとは他と差別化するためのシンボルであるため、特異な個性が重要です。凡庸なロゴでは、見た者の記憶に残らず顧客との接点を得にくいでしょう。
3.感情面
ロゴは機能面だけでなく、見る人に感情的な影響を与えることが重要です。優れたロゴは人の心を動かし、長く愛されるようになります。
安心感
想定したターゲットに響くことが前提となりますが、一般的には過度に奇抜だったり恐怖や危険を感じるデザインは避けるべきです。
信頼感
これも安心感と同様で、ターゲットの信頼を得られるかどうかが重要です。例えば自己主張だけが強いロゴは信頼を得られない場合があります。
親しみやすさ
身近に感じられる要素があるか検証します。「分かる人だけに分かればよい」という排他的な姿勢は避けます。(あえてそれを狙うケースもありますが)
かっこ良さ
カッコ良さの基準は人それぞれですが、ペルソナ分析などでターゲットの好みや志向に合った「かっこ良さ」を意識する必要があります。「この企業の商品を買うと嬉しい」「持っているだけで幸せになれる」「ロゴを見ただけで欲しくなる」そんな感情を醸成できるブランドが理想です。
ユニークさ
ロゴは唯一無二の存在であることが重要です。競合他社と比べて差別化できているか、個性が際立っているか検証します。同じ業態であればロゴも似てしまうことはよくあります。その中で自社の特徴をきちんと表現できているか、同じ集団の中でいかに選ばれるかが重要です。
ロゴデザインのプロセス
1.ヒアリング
まずは企業について徹底的に理解することから始めます。どのような事業を展開しているのか、どのような未来を目指しているのか、現状の課題は何か、担当者に深くお話を伺います。
2.リサーチ
業界の動向や競合他社を徹底的に調査します。3C分析やSWOTなどを使って企業と外部環境との関係性を把握し、より具体的で実現可能な戦略の立案につなげます。同時に競合先のロゴデザインの傾向をポジショニングマップで視覚化し、自社のロゴデザインの方向性を定めます。
3.価値規定
企業が本当に大切にしている「価値」や「独自性」を見いだし、言語化します。事実や特徴、機能的価値、社会的価値、情緒的価値といった観点から独自の個性を導き出します。
4.テーマ策定
価値規定やペルソナ分析をもとに、ロゴのコンセプトやテーマを定めます。
5.アイデア出し
決定したテーマに沿って、ひたすらアイデアを出します。5W1Hの視点やオズボーンのチェックリスト、時にはブレインストーミングなどを用いながら、ラフスケッチに落とし込みます。
6.造形
スケッチの中から最適なものを選び、デジタルデータとして形にしていきます。
7.プレゼンテーション
完成したロゴ案を提案し、デザインに込めた想いを伝えます。
8.ブラッシュアップ
フィードバックをもとに修正やディテールの調整を行い、デザインを磨き上げます。再度プレゼンテーションを行い、最終的なデザインを決定します。
9.運用マニュアル
ロゴの正しい使い方をまとめたマニュアルを作成します。目的は、使用者や媒体によってブランドイメージがブレないようにすることです。
10.ツール展開
完成したロゴを、名刺やウェブサイトなどの各種ツールへ適用していきます。
11.フィードバック
ロゴの運用開始後も、多方面からの反応をピックアップし、必要に応じて改善を検討することが重要です。
アイディア出しのアプローチ
アイディア出しの思考プロセスは人それぞれですが、スタイルメントでは以下のようなアプローチで行っています。
ここでは例として焼き芋屋のブランドロゴを作る場合で考えてみます。
1.キーワードから入る
焼き芋屋であれば、「温かい」「田舎」「甘い」「素朴」「おいしい」「食物繊維」「日本の文化」「秋」「落ち葉」「健康」といったキーワードを挙げます。 それらを複数組み合わせたり、意外な組み合わせを試したりすることで、キーワードを具現化できる形やモチーフを探していきます。 もちろん、その企業独自の理念や特徴(例えば有機栽培のさつまいも使用、味に絶対の自身あり、など)があれば、それらも優先的に参考にします。
2.イメージから入る
焼き芋を取り巻く環境や、食べる際の感情といったユーザーの利用シーン、さらに「手軽なおやつ」「家族の団欒」「秋の味覚」といった焼き芋に対するイメージから、アイデアを探ります。
3.形から入る
キーワード、社名、商品名に加え、ロゴやマーク、シンボル、アイコン、イラストなどの組み合わせで画像検索を行います。例えば「焼き芋 ロゴ」「IMO ロゴ」「イモ アイコン」など、さまざまな組み合わせで検索し、ヒントとなる画像を多数収集します。これらの画像を後で見返し、デザインの参考となる形を見つけて、そこから形を発展させていきます。既存のロゴと似ないようにするためのリサーチも兼ねています。
4.タイプフェイスから入る
店名が「IMOYA(芋屋)」の場合、文字「芋」「IMO」「いも」と、イメージとしての「あたたかい」「素朴」などを組み合わせ、考えられる書体を片っ端から試してみます。実際に打ってみて、どのようなイメージや感情を喚起するかを客観的に分析し、良いものを残します。自分のパソコンにない書体でも、ネット上のフォント配布サイトでプレビューすることができます。イメージに近い書体が無い場合は一から作字することもあります。
5.好みから入る
ロゴは企業のものであると同時に、デザイナーの個性も反映されるべきだと考えています。そのため、理屈にとらわれず、自分の好みや得意な造形スタイルを盛り込んだ案も入れるようにしています。
例えばキャラクターを創るのが得意なデザイナーは、焼き芋を食べてる可愛らしい女の子をシンボルマークにするかもしれません。
6.色から入る
コンセプトを表現するうえで色が重要な要素である場合に限り、色を軸に案を出すこともあります。たとえば「むらさき芋」という商品のロゴで、紫色がコンセプト上重要な要素であると考えられる場合、単色はもちろん、グラデーションや階調色など、さまざまな配色の可能性を検討します。ただし、白黒でもコンセプトが伝わるかを考慮したうえで提案します。
以上の6つのアプローチを、単独または複数組み合わせて案出しを行います。
デザインの追い込み
手を動かす
頭で考えているだけでは、必ずしも良いアイディアは出てきません。とにかく思いついたものをたくさんスケッチします。その中から新たな発想が生まれることもよくあります。ここで重要なのは、スケッチで形を決め過ぎないことです。この段階ではまだ多くの選択肢に過ぎないため、フラットな感覚で思考をひたすら紙に落としていきます。
発展させる
スケッチしたアイディアを発展させます。ひとつの種からさまざまな種類の芽が育つイメージです。大きさを変えたり、反転させたり、角度を変えたり立体にしたり、線や面に変換したり、整列させたり分解したり、細く太く、鋭く丸く、ラフまたは整頓したり、個性を強めたり、あらゆる試行錯誤を繰り返します。この段階がデザイナーにとって最も楽しい時間です。
フィニッシュ
発展させた案を絞り込んでいきます。前述のデザインの観点「構成面」「機能面」「感情面」に照らし、可能性のある案を20〜30案ほどピックアップします。それら清書し、形を整え、必要に応じてイラストレーターなどでデータ化します。
見直してみる
デザインしたものを改めて見直します。複数のデザイナーで案出しを行う場合は、各自の案を持ち寄り、相談しながら似た案をまとめたり、客観的・論理的・審美的な観点から再考し、半分程度まで絞ります。時にはスケッチまで戻ってやり直すこともあります。
コンセプトを組み立てる
最後に、デザインの考え方や造形上の表現意図を整理し、コンセプトを言語化します。
ロゴデザインは未来への羅針盤
以上、スタイルメントのロゴデザインの手法について簡単にまとめてみました。
ロゴデザインは、企業のブランディングに欠かせない重要なプロセスのひとつです。ウェブサイトや広報などの対外的なビジュアルコミュニケーションのツールとしてだけでなく、社員の帰属意識を高めるといった社内的な側面も担っています。
私は、ロゴは企業の過去と未来をつなぐ架け橋であり、これから進むべき道を示す羅針盤のような存在だと考えています。ロゴデザインを見直してみることは、過去の遺産を受け継ぎながら、変化を恐れずに新しい未来へ進む、そのきっかけとしてきっと役に立つことでしょう。
自分の会社のロゴ、果たして今の会社に合ってるのかどうか、ぜひ客観的な視点で見直してみてはいかがでしょうか。
スタイルメントが制作したロゴデザイン
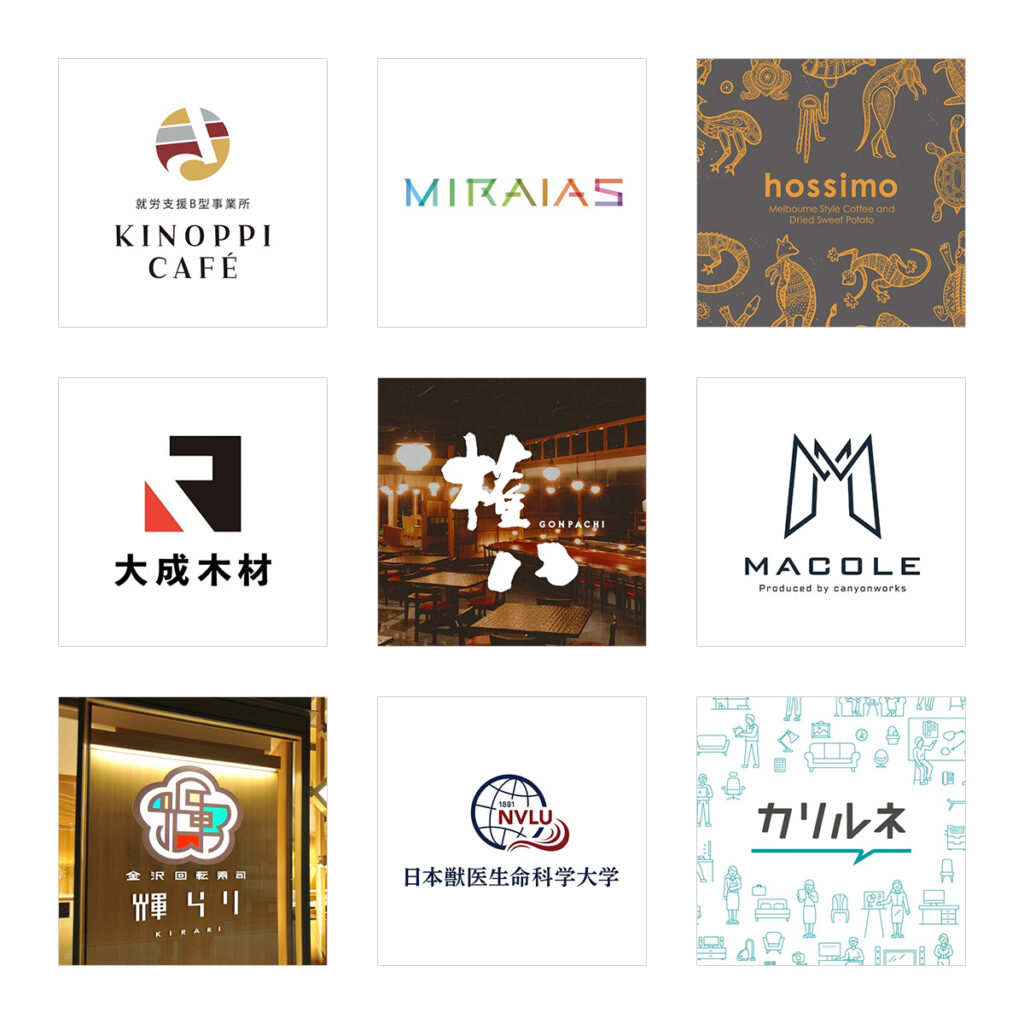
ロゴマーク制作実績一覧はこちら。
ロゴマークの刷新をご検討中の方へ
ロゴに込めたい想いやブランドの核となる価値の整理から、コンセプト立案、ロゴデザイン、名刺やWebサイトへの展開サポートまで、トータルでご提案させていただきます。まだイメージが固まっていない場合も、お気軽にご相談ください。
<サービスページ>
ロゴマーク制作|サービスページ
<制作に関するお問い合わせはこちらから>
お問い合わせフォーム





